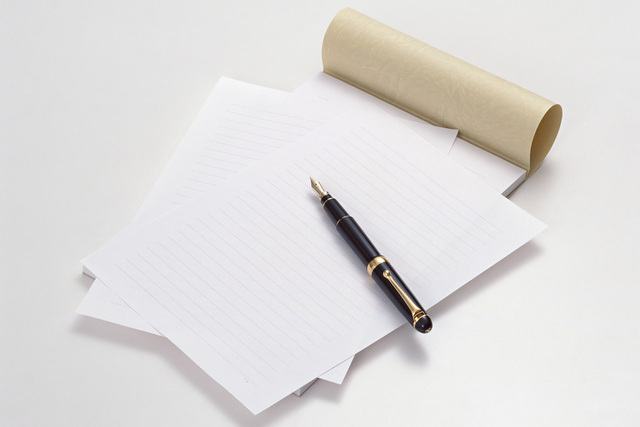広島の遺産分割・遺言・相続税は、遺産相続に強い私たち弁護士・税理士・FP(広島市中区)にお任せください。専門家が相続の問題に共同して対応します。
弁護士(山本総合法律事務所) :広島市中区大手町2-8-1-7階
税理士(山本直輝税理士事務所):広島市中区国泰寺町1-5-31-3階
電話受付時間
(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要予約)
初回ご相談は45分無料
082-546-0800
遺言による相続対策

「相続」は「争続」と呼ばれることもあることを、ご存じでしょうか。
「争続」と呼ばれるのは、文字通り、残された家族同志が争うケースが珍しくないからです。
「うちの家族は、仲が良いから大丈夫」とお考えの方もいらっしゃると思います。しかし、現実には、仲が良かった家族が、相続をきっかけに争うケースが数多くあります。これは、遺産が多いご家庭でも、そうでないご家庭でも、同じです。
自分の相続で家族が対立するのは、亡くなられた方にとって、もっとも悲しい結末ではないでしょうか。
こうした事態を避けるための最も適切な方法は、法律に従って遺言(いごん、ゆいごん)を作成することです。遺言を作成しておけば、財産の分け方は遺言書どおりとなりますし、残されたご家族も納得しやすいため、相続人間で争いが生じる可能性は低くなります。ご家族の中が良いからこそ、遺言を作成して、紛争の火種が生じないようにすることが重要です。。
また、自分が亡くなった後に、財産を誰にどれだけあげたい、というお気持ちをお持ちの方も多くいらっしゃると思います。こうしたお気持ちは、遺言を作成することで実現できます。
さらに、事業を営んでおられる方は、後継者に円滑に事業を引き継ぐために、遺言書の作成が効果的な手段の一つとなります。
このように、遺言を作成することは、遺言を作成する方にとっても、残されたご家族にとっても、事業承継においても、非常に大切なことです。
このページでは、遺言書の作成について、ご説明します。
遺言により紛争を予防できる

「遺産は法律にしたがって分ければ、もめないはずだ」
このようにお考えの方はいらっしゃらないでしょうか。確かに、民法では、どの相続人がどれだけの割合の財産を相続できるかについて、定められています(これを「法定相続分」といいます)。
しかし、この規定にしたがって遺産を分けようとしても、争いは生じます。
(例)相続財産(遺産)が、①自宅の土地建物と、②預金のケース
自宅の土地建物を物理的に分割することは、現実的に不可能です。そうすると、相続人間で協議して、自宅を売却するのか、相続人の誰かのものにするのか、自宅の価値(評価額)をいくらにするのか、自宅をもらわない人は代わりに預金をいくら取得するのかなどについて、協議して決める必要があります。この遺産分割協議は、各相続人の利害に関わるため、時間がかかることが珍しくありません。そして、仮に協議がまとまらなければ、法的手段をとることになります。
法定相続分に従って遺産を分割するにしても、分割の方法は様々ありますので、相続人同士が争う原因となります。
このように、遺言がない場合には、法律の規定にしたがって財産を分けようとしても、争いが起き得るのです。
では、遺言がある場合には、どのようになるのでしょうか。
遺言では、どの財産を、誰に相続させるかを、決めることができます。そのため、適切に遺言書を作成すれば、相続人同士の争いが生じるリスクを低下させることができます。
遺言により遺産を適切に分ける

遺言がない場合には、法定相続分にしたがって遺産を分けることになります。
しかし、それが常に妥当であるとは限りません。
例えば、実家の稼業をついでくれた子や、自分の身の回りの世話をしてくれた子に多くの遺産をあげたい、自分と絶縁関係にある子にはあまり遺産をあげたくないなど、遺産の分け方についてお考えをお持ちの方はおられると思います。
法律の定める法定相続分は、各ご家庭のご事情とは関係なく、一律に定められています。しかし、ご家庭のご事情によっては、法定相続分とは違う割合で財産を分ける方が、妥当な場合もあります。
また、例えば、遺言により、ご自身が亡くなられた後、残された奥様が自宅に住み続けられるようにする方法もあります。
また、正式には結婚していないけれども、事実婚(内縁)関係にある方がいらっしゃる場合にも、内縁の配偶者に遺産を引き継がせるためには遺言が必要となります。内縁関係にある方は、法的に相続人ではないため、原則として財産を相続することができないからです。
このように、遺言を作成すれば、遺言を作成する方のお気持ちに沿った、適切な遺産の分配が可能となります。
事業承継を円滑・適切に実施できる

会社を個人で経営されている個人事業主の方が亡くなられた場合、その方の名義の預金口座は凍結されます。しかし、遺言がない場合、遺産分割協議がまとまるまでは、原則として、預金を引き出すことができません。そうすると、従業員の給与や取引先への支払いが滞ることになります。
また、株式会社の場合、故人が保有していた株式を誰が相続するかについて争いとなれば、会社経営が立ち行かなくなることもあります。
例えば、株式会社のオーナーが、長男を跡継ぎとして考えていたとしても、長男は、株式を相続しなければ、経営権を失うことにもなりかねません。
また、速やかに株式を相続しなければ、会社経営が停滞することにもなります。しかし、遺言がなければ、長男が株式を相続できるとは限りませんし、相続できるとしてもそれまでに時間がかかることもあります。
また、遺産分割協議等により株式の帰属が決まるまでは、相続財産である株式は、各相続人による「準共有」の状態となります(それぞれの株式について、各相続人が権利を持つ状態です)。このとき、株式の権利を行使するには、権利行使者を、共有持分の過半数の賛成により定めることになります。そのため、場合によっては、長男以外の相続人が結集して権利行使者を定め、長男を会社の取締役を解任し会社から排除する、といった事態が生じる可能性もあります。さらに、株式をめぐり相続人同士が争っていると、会社の信用が低下するおそれもあります。
これらは、遺言がない場合に起こるトラブルの一例です。
こうしたトラブルは、例えば「特定財産承継遺言」(※)を作成し、株式や預金を誰が相続するかを定めておくことで、回避できます。
会社経営者の方は、個人事業主であっても、株式会社の経営者であっても、遺言を作成しておく必要性が非常に高いといえます。
なお、会社の事業承継については、他にも、相続税対策や、オーナーの方にどういった権限を残すかなどを考慮し、様々な対策を講じる必要があります。
(※)民法改正(2019年7月1日施行)により、特定の遺産について、遺産の分割方法の指定として特定の相続人に相続させる遺言を、「特定財産承継遺言」と呼ぶことになりました。そして、この遺言により相続した遺産のうち、法定相続分を超える部分を取得したことについては、登記等の対抗要件を備えない限り、第三者に対抗(主張)できないことになりました(従前の判例・実務の取り扱いの変更)。
遺言書の作成による相続対策
遺言にはいくつか種類があります。主なものは、①自筆証書遺言と、②公正証書遺言です。
(詳しくは遺言の基本をご覧ください。)
このうち、②公正証書遺言の場合、次のメリットがあります。
・公証役場で遺言の原本が大切に保管される。
・公証人が遺言者の意思能力を確認するため、遺言の無効が争われるリスクが低下する。
・死後に家庭裁判所の「検認」という手続を経なくても、相続手続を開始できる。
・公証人による出張対応があるため、入院中でも利用できる。
広島で公正証書遺言を作ることができる公証役場は、広島市(広島公証人合同役場)、東広島市、呉市、尾道市、福山市、三次市の6か所にあります。
これに対し、①自筆証書遺言は、文字通り、ご自身が手書きで遺言書を作成するものです。
従前、自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認手続が必要であることや、遺言書が紛失するリスクがあるものでした。
しかし、令和2年7月10に施行された「法務局による遺言書の保管等に関する法律」(通称、遺言書保管法)の自筆証書遺言保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットの一部が解消されることになりました。
遺言書保管法の主な内容は、次のとおりです。
①法務局が自筆証書遺言の遺言書を保管する。
②家庭裁判所の検認手続が不要になる。
③法務局の遺言書保管官が、自筆証書遺言の方式に適合しているかについて、外形的な確認をする(内容の確認はされません)。
④相続開始後に相続人等に通知が届く(通知は次の2種類)
ア 関係遺言書保管通知:遺言者が死亡し、相続人等のうちの一人が、遺言書保管書で遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、相続人全員に対して、遺言書が保管されているとの通知される。
イ 指定者通知:遺言書がこの通知を希望している場合、通知対象者に対し、遺言書保管所において法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、遺言書が保管されているとの通知がされる。
もっとも、自筆証書遺言は、公正証書遺言とは異なり、公証人による遺言者の意思能力の確認がありません。そのため、遺言者の判断能力が疑われる等の場合には、遺言の有効性をめぐる紛争のリスクが軽減されません。
また、自筆証書遺言の場合、遺言書を手書きで作成する必要があるため(財産目録を除く)、分量が多い遺言書を作成する場合や、手が不自由な方の場合には、ご負担が大きくなります。
上記のどちらの方式で遺言書を作成するとしても、遺言の内容をどうするか、どのように遺言書を記載するか等については、専門的な判断が必要です。
専門家に相談をせずに遺言書を作成したために、遺言書の意味の解釈をめぐる激しい紛争が生じることも珍しくありません。
そのため、相続問題に強い弁護士へのご相談をお勧めします。
関連するページ
無料相談のご予約・お問い合わせはこちら
弁護士・税理士・FPへの無料相談はこちらからお申込みください
初回ご相談は45分無料
082-546-0800
山本直輝税理士事務所につながりますので、「相続のホームページを見た」とお伝えください。
※法律問題のみのご相談の方は、山本総合法律事務所(082-544-1117)にお電話ください。
受付時間:(平日)9:00〜18:00
夜間・休日対応可(要事前予約)

相続に強い専門家が、相続税対策・遺産分割・遺言などの相続問題に共同対応
082-546-0800
(平日)9:00~18:00
相談料:平日初回45分無料
山本直輝税理士事務所につながります。「相続のホームページを見ました」とお伝えください。
※法律問題のみご相談の方は、山本総合法律事務所(082-544-1117)にお電話ください。
広島の弁護士と税理士による相続相談
山本総合法律事務所
広電「袋町」電停目の前
アストラムライン「本通駅」徒歩3分
広島バスセンター徒歩7分
広島市中区大手町2-8-1大手町スクエア7階(山本総合法律事務所HPはこちら)
082-544-1117